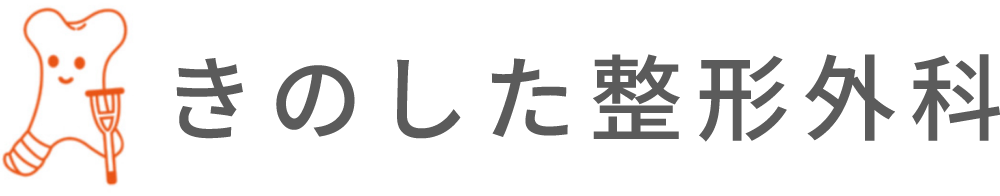首・肩の痛みでお悩みの方へ

首の痛みは、日常的に多くの方が経験する不調のひとつです。デスクワークやスマートフォンの長時間使用による姿勢の乱れから、加齢やスポーツ外傷まで、原因はさまざまです。首の不調を放置してしまうと、肩や腕への広がり、頭痛や手のしびれなど、全身に影響が及ぶこともあります。
また肩の痛みは、年齢や性別を問わず多くの方にみられる症状で、日常生活における動作や睡眠、仕事にまで支障をきたすことのある不調です。原因は単なる「こり」から関節の炎症、腱や靱帯の損傷、神経障害に至るまで幅広く、適切な診断と治療が必要となります。
首の痛みの原因となる生活習慣や外傷、障害など
現代人の首の痛みは、日常生活の姿勢や動作のクセが大きく影響しています。長時間のパソコン作業やスマートフォンの操作、うつむき姿勢での読書や家事など、首を前に突き出した姿勢が続くことで、筋肉や関節に大きな負担がかかります。こうした慢性的な負担は、首や肩の筋肉の緊張を生み、痛みやこりを引き起こす原因になります。
また、交通事故や転倒、スポーツでの急激な衝撃による外傷も首の痛みの一因です。とくに「むち打ち症(頚椎捻挫)」のような外力による頚部の損傷は、見た目に異常がなくても内部で筋肉や靱帯に炎症を起こしている可能性があります。加齢による椎間板や関節の変性、筋力の低下なども、首の痛みを招く要因として注意が必要です。
首の痛みを引き起こす疾患
頚椎症
加齢や使いすぎにより、頚椎の椎間板や骨が変性し、神経の通り道が狭くなることで起こる病気です。肩こりのような鈍い痛みに加えて、進行すると腕のしびれや筋力低下、細かい作業が困難になるといった神経症状がみられることがあります。悪化すると、頚椎症性脊髄症という脊髄の障害に進行することもあります。
頚椎椎間板ヘルニア
頚椎と頚椎の間でクッションの役割を果たしている椎間板が飛び出し、神経を圧迫することで、首の痛みとともに肩から腕、手にかけてしびれや痛みが放散する疾患です。咳やくしゃみで症状が強くなることもあり、放置すると筋力低下や感覚麻痺につながる場合もあります。
ストレートネック(スマホ首)
本来は前弯しているはずの頚椎がまっすぐになり、頭を支えるために首や肩の筋肉に過剰な負担がかかる状態です。パソコンやスマートフォンを長時間使用する習慣が影響しており、慢性的な肩こり、頭痛、首の痛みの原因となります。
首の痛みに伴ってみられやすい症状
首の痛みに加えて、以下のような症状が同時に現れることがあります。
- 肩や背中への放散痛
- 腕や手のしびれ・感覚の鈍さ
- 握力低下や細かい作業の困難さ
- 頭痛、めまい、耳鳴り
- 集中力の低下や睡眠障害 など
これらは、首の神経が圧迫されることによって生じる神経症状(神経根症や脊髄症)であることもあります。こうした症状がある場合は、単なる肩こりや疲労とは異なる可能性があるため、専門的な診断が必要です。
肩の痛みの原因となる生活習慣や外傷、障害など
肩は可動域の広い関節である反面、構造が複雑で負担がかかりやすく、さまざまな原因で痛みを生じます。とくに多いのが、長時間のパソコン作業やスマートフォン操作、デスクワークによる姿勢の乱れや筋緊張によるものです。また、スポーツや肉体労働によって肩関節に繰り返し負荷がかかることでも、腱や靱帯の炎症が起こることがあります。
加齢に伴う筋肉・腱の変性や、関節の変形も肩の痛みの大きな要因です。40代以降に増加する「四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)」や、腱板断裂、変形性肩関節症などがこれにあたります。転倒や外傷による打撲・骨折・脱臼が原因になるケースも見られます。
肩の痛みを引き起こす疾患
肩関節周囲炎(いわゆる四十肩・五十肩)
40〜60代に多く、はっきりとした原因がなく肩の動きが制限され、炎症による痛みが長期に続く疾患です。初期は肩を動かしたときに痛みがあり、進行すると夜間痛や可動域の制限が強まり、衣服の着脱や洗濯物を干すなど家事の動作が困難になります。自然に治ることもありますが、治るまでに1年以上かかることもあり、また可動域が狭いままで固まってしまうことも多く、早期からのリハビリが重要です。
腱板断裂
肩の筋肉と骨をつなぐ腱板が、加齢や繰り返しの動作で傷つき、断裂してしまう状態です。腕を挙げるときの引っかかり感や痛み、力が入らないなどの症状が現れます。完全断裂の場合は、筋力低下が顕著で、手術による修復が必要になることもあります。四十肩・五十肩と症状が似ているため、見極めることが重要です。
変形性肩関節症
肩の関節軟骨がすり減ることで関節が変形し、慢性的な痛みや動かしにくさを生じます。加齢が主な原因で、関節に負担のかかる仕事やスポーツ歴がある方に多くみられます。進行すると日常生活にも支障が出るため、早期の診断と治療が大切です。
詳しくはこちら肩の痛みに伴ってみられやすい症状
肩の痛みに加えて、以下のような症状がみられることがあります。
- 肩の可動域の制限(腕が挙がらない・回せない)
- 腕のしびれや脱力感
- 夜間の痛みで眠れない
- 動作のたびに「引っかかり」や「音」がする
- 首から腕にかけての放散痛 など
肩の痛みの治療は、軽度であれば、消炎鎮痛薬や湿布の処方、生活指導による安静で改善が見込めます。痛みが強い場合には、関節内注射(ヒアルロン酸・ステロイド)を用いた集中的な消炎処置を行うこともあります。
腱板損傷や四十肩・五十肩では、関節の柔軟性や筋力を保つための運動療法・リハビリテーションが非常に重要です。肩の痛みは「年のせい」とあきらめがちですが、適切な治療と運動により改善するケースが多くあります。放置すると関節の動きが制限されたまま固まってしまうこともあるため、日常生活での違和感や痛みを覚えた際は、ぜひ早めにご相談ください。
背中の痛みについて

背中の痛みは、日常的によく見られる症状でありながら、その原因や程度は人によって大きく異なります。姿勢の乱れや筋肉疲労によるものから、背骨や神経に関わる病気、内臓の異常が隠れている場合もあり、放置することで悪化することも少なくありません。
当院では、整形外科の専門的な視点から、背中の痛みの背景にある原因を見極め、適切な検査と治療を行っています。慢性的な違和感や急な強い痛みがある場合は、早めにご相談ください。
背中の痛みの原因となる生活習慣や外傷、障害など
背中の痛みは、長時間の同一姿勢(デスクワーク・スマホ操作・読書 など)や、猫背などの不良姿勢、重い荷物の持ち運び、無理な体勢での作業、寝違えといった、日常的な動作によって筋肉や靭帯に負担がかかることで生じることが多くあります。
また、筋力の低下や柔軟性の欠如により、背骨を支える筋肉が疲労しやすくなり、慢性的な背部痛につながります。さらに、転倒や交通事故、スポーツ中の外傷により、筋肉の損傷や肋骨の骨折、脊椎の圧迫骨折などが起こることもあります。さらに加齢に伴う背骨の変性や、背骨の歪み(側弯症や円背)も痛みの原因になるため、年齢を重ねるごとに注意が必要です。
背中の痛みを引き起こす疾患
筋・筋膜性腰背部痛(筋肉性の痛み)
日常生活の姿勢不良や過労、睡眠不足、ストレスなどによって、筋肉や筋膜が緊張し続けることで発症します。鈍い痛みや重だるさが主な症状で、安静にしていても違和感が続くことがあります。とくにデスクワーク中心の方に多く見られます。
胸椎椎間関節症・椎間板障害
背骨の関節や椎間板がすり減ることで、炎症や関節の不安定性が生じ、背中の痛みを引き起こします。体をねじったり反らしたときに痛みが増すのが特徴で、放置すると慢性化したり、神経に影響が及ぶ可能性があります。
脊椎圧迫骨折(とくに高齢の方)
加齢により骨がもろくなった状態である「骨粗鬆症」により、軽い尻もちや立ち上がり動作でも背骨がつぶれてしまう骨折です。背中や腰に急激な痛みが出現し、動くと強く痛むため、動作が制限されます。放置すると姿勢の悪化や内臓への影響も懸念されます。
詳しくはこちら背中の痛みに伴ってみられやすい症状
背中の痛みは、単独で起こる場合もありますが、以下のような症状を伴うこともあります。
- 肩や腰、首への放散痛
- 呼吸時や咳・くしゃみでの痛み
- 背中から胸にかけてのしびれや違和感
- 姿勢が崩れて背中が丸まる
- 下肢のしびれや脱力感(神経症状) など
これらの症状がある場合、背骨の神経に関わる病変や骨折の可能性もあるため、早めの診察と検査が必要です。
また、まれに内臓(心臓・肺・腎臓・消化器 など)に関連した痛みが背中に現れることもあるため、整形外科的な原因と区別することが大切です。痛みが長く続く、繰り返す、他の部位へ広がっているという場合は、放置せずに一度受診することをおすすめします。
腰の痛みについて

腰の痛み、いわゆる「腰痛」は、日本人の多くが一度は経験する症状であり、整形外科の受診理由としても非常に多い訴えです。長時間のデスクワークや家事、運動不足、加齢による変化など、日常生活の中に原因が潜んでいることも少なくありません。
一時的な痛みで済む場合もありますが、なかには椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症といった病気が隠れていることもあります。慢性的に続く腰の違和感や、動くたびに痛みが増すなどの症状があれば、早めに整形外科を受診して原因を見極め、適切な治療を受けることが大切です。
腰の痛みの原因となる生活習慣や外傷、障害など
腰痛の大半は、日常の姿勢や動作のクセ、筋力低下、体重の増加、ストレスなどの生活要因が関係しています。長時間の座位姿勢や中腰作業、重い物を持つ動作を繰り返すことで腰部に過剰な負荷がかかり、筋肉や靱帯、椎間板に微細な損傷を起こして痛みを引き起こします。
また、加齢とともに腰椎や椎間板が変性していくことで、慢性的な腰痛を抱える人も増えていきます。ぎっくり腰(急性腰痛症)や腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、骨粗鬆症による圧迫骨折など、腰痛の背景にはさまざまな病態が存在します。またスポーツや転倒による外傷、手術後の後遺症、長期の安静による筋力低下も腰の痛みの原因になります。
腰の痛みを引き起こす疾患
急性腰痛症(ぎっくり腰)
急な動作や重い物を持ち上げた際に発症し、突然腰に激痛が走るのが特徴です。筋肉や靱帯の軽度な損傷によることが多く、通常は数日から1~2週間で自然回復しますが、繰り返す場合や動けないほどの痛みがある場合は注意が必要です。
腰椎椎間板ヘルニア
腰部の背骨の腰椎と腰椎の間にある椎間板が飛び出して神経を圧迫する病気です。腰の痛みに加えて、足のしびれや放散痛、感覚異常、筋力低下が見られます。放置すると神経障害が進行する恐れがあるため、早期の診断と治療が重要です。
腰部脊柱管狭窄症
加齢に伴い背骨の中の神経の通り道(脊柱管)が狭くなり、神経が圧迫されることで、立っているときや歩行時に足のしびれや痛み、間欠性跛行(歩くと足が痛くなり、休むと軽快する)という特徴的な症状がみられる疾患です。50代以降に多く、進行すると歩行困難になることもあります。
腰椎圧迫骨折(骨粗鬆症性)
高齢の方に多く、骨密度が低下した背骨が、尻もちや軽い衝撃だけで潰れてしまう骨折です。腰や背中に鋭い痛みが出て動けなくなることもあり、骨粗鬆症の治療と並行して適切な管理が求められます。
詳しくはこちら腰の痛みに伴ってみられやすい症状
腰痛に加えて、次のような症状が同時に現れることがあります。
- お尻や脚への放散痛、しびれ
- 足の力が入りにくい、つまずきやすい
- 長時間立っていると痛みが強くなる
- 寝返りや起き上がり時の強い痛み
- 尿漏れ・排尿障害(重症の神経圧迫による) など
こうした症状は、神経の障害が関係している可能性があるため、早期の整形外科的評価と治療が必要です。一見単なる腰痛のように思えても、しびれや感覚の異常を伴う場合には、注意が必要です。
腰の痛みは、放置すると慢性化し、日常生活の質を大きく損なう原因になります。気になる症状があるときは我慢せず、早めにご相談ください。
手の痛み・しびれについて

「手がしびれる」「指がうまく動かない」「手首が痛む」といった症状は、日常生活に大きな不便をもたらすだけでなく、神経や関節、腱などに異常があるサインであることも少なくありません。
スマートフォンやパソコンの長時間使用、加齢による関節や腱の変性、神経の圧迫や炎症など、手の痛みやしびれにはさまざまな原因が潜んでいます。早期に原因を特定し、適切に対処することが、機能の回復と悪化の防止につながります。
手の痛み・しびれの原因となる生活習慣や外傷、障害など
手は日常生活のあらゆる動作に関わる部位であり、繰り返しの作業や長時間の使用による負荷が集中しやすい部分です。そのため、腱や関節、神経に微細な損傷が蓄積し、痛みやしびれの原因となります。
具体的には、パソコンのキーボード操作やスマホの使用、細かい手作業、家事、スポーツなど、指や手首を酷使する生活習慣が関与します。また、転倒などによる手の打撲・骨折、神経を通すトンネル状の構造(手根管や肘部管 など)での神経圧迫、加齢による関節の変形や腱の摩耗も痛みやしびれの原因になります。
手の痛み・しびれを引き起こす代表的な疾患
手根管症候群
手のひら側の手首を通る「正中神経」が、靭帯や腫れによって圧迫されることで、親指から中指にかけてのしびれや痛み、指先の感覚鈍麻が起こる病気です。朝方の強いしびれや、ボタンを留めにくい、物を落としやすいといった症状が特徴です。更年期の女性や妊娠中の方に多く見られます。
詳しくはこちら肘部管症候群
肘の内側で「尺骨神経」が圧迫される疾患で、小指や薬指のしびれ、握力の低下、細かい作業がしにくくなるといった症状が現れます。肘を長時間曲げた姿勢や、打撲、加齢による骨の変形が原因となります。進行すると筋萎縮が起こることもあるため、早期治療が重要です。
ばね指
指を曲げ伸ばしする腱と腱鞘が炎症を起こし、動かすとカクッと引っかかるような症状が出る疾患です。指を曲げたまま伸ばしにくくなることや、痛みを伴うことがあります。家事や手作業が多い方、更年期、妊娠出産期の方、糖尿病のある方に多くみられます。
母指CM関節症
親指の付け根の関節(手根中手関節)が変形することで、物をつまむ、ひねる、開けるといった動作が困難になる病気です。更年期以降の女性に多く、進行すると関節の変形や腫れが目立つようになります。
詳しくはこちら関節リウマチ
免疫の異常によって関節の内側に炎症が起こり、主に手や指の関節に腫れや痛みを生じる病気です。原因ははっきりしていませんが、遺伝や感染、ホルモンの関与が指摘されています。放置すると関節が変形し、日常生活に支障をきたすため、早期診断と治療が重要です。
詳しくはこちら手の痛み・しびれに伴ってみられやすい症状
手の症状が進行すると、以下のような機能障害を引き起こすことがあります。
- 手指のしびれや感覚の低下
- つまむ・握る・ボタンを留めるなどの細かい動作の困難
- 筋力の低下(握力減少)
- 手の変形、腫れ、熱感
- 夜間や早朝の強いしびれ、痛みで目が覚める など
これらは日常生活に大きな影響を及ぼすだけでなく、進行すると手術が必要になることもあるため、軽症のうちにご相談いただくことが大切です。
手は日常生活のあらゆる動作に関わる大切な部位です。「しびれは我慢できるから」「少し痛いだけだから」と放置していると、知らず知らずのうちに進行し、回復に時間がかかる場合もあります。当院では手の専門的な診療を行っており、日本手外科学会認定 手外科専門医が早期診断と的確な治療をサポートいたします。少しでも気になる症状がある方は、お早めにご相談ください。
膝・股関節の痛みについて

膝の痛みは、中高年の方を中心に非常に多く見られる整形外科的な症状のひとつです。階段の上り下り、正座や立ち座り、歩行など、日常生活のあらゆる場面で膝は重要な役割を果たしており、少しの痛みでも大きな不自由を感じやすい部位です。
一方、股関節は体の中でもとくに大きな関節で、やはり上半身の重さを支えながら脚を動かすという重要な役割を果たしており、こちらも痛みが出ると歩行や起立、階段の昇降など日常動作に大きな支障をきたします。
こうした運動器の障害によって移動が難しくなり、活動量が低下すると、生活の質も大きく損なわれ、高齢の方では認知症の引き金となる場合もあります。そのため、膝や股関節の痛みは放置せず、早期に治療を行うことが重要です。
膝の痛みの原因となる生活習慣や外傷、障害など
膝関節は、体重を支えながら大きな動きを担う関節であるため、日常生活や運動によって常に負担を受けています。長年にわたる使い過ぎや加齢に伴う軟骨のすり減り、肥満による負荷の増加などが痛みの原因となることが多く、とくに40代以降では変形性膝関節症が増加します。
また、スポーツや転倒、交通事故などで膝に強い力が加わることで、靱帯や半月板を損傷し、急性の膝の痛みが生じることもあります。運動をしている若い世代では、膝周囲の腱の炎症(ジャンパー膝 など)やオスグッド病といった成長期特有の膝痛も見られます。日常の姿勢や歩き方のクセ、筋力低下や柔軟性の不足も膝に負担をかける要因です。
膝の痛みを引き起こす代表的な疾患
変形性膝関節症
膝関節の軟骨が加齢や使いすぎによってすり減り、関節が変形して痛みを生じる慢性疾患です。中高年の女性に多く、初期は立ち上がりや階段昇降時の痛み、進行すると歩行困難や関節の腫れ、変形が目立つようになります。悪化すると日常動作が著しく制限されるため、早期からの治療と予防が重要です。
詳しくはこちら半月板損傷
膝関節内のクッションの役割を果たす半月板が、加齢やスポーツ外傷により断裂することで痛みや腫れ、ひっかかり感が現れます。損傷の程度によっては膝がロックされて動かなくなることもあります。放置すると変形性関節症に進行する可能性があるため、早めの診断と処置が必要です。
靱帯損傷(前十字靭帯・内側側副靱帯 など)
スポーツや転倒、ねじれ動作で膝の靱帯が損傷すると、激しい痛みや腫れ、膝の不安定感が生じます。完全断裂の場合は自然治癒が難しく、手術が必要になることもあります。若年層の運動中のけがとして多くみられます。
膝の痛みに伴ってみられやすい症状
膝の痛みに加えて、以下のような症状がみられることがあります。
- 関節の腫れや熱感
- 動かしたときの「ゴリゴリ」音やひっかかり感
- 膝の不安定感や力が抜ける感覚
- 膝が伸びない・曲がらない
- 正座やしゃがみ込みが困難になる
- 歩行中につまずきやすくなる など
こうした症状が継続・悪化する場合は、関節内部の構造的な異常がある可能性があるため、整形外科での検査・治療をおすすめします。
膝の痛みは年齢に関係なく誰にでも起こり得るものですが、早期の対応によって進行を防ぎ、生活の質を維持することが可能です。「年だから仕方ない」「少し休めば治る」と軽く考えず、気になる症状がある方は、ぜひお早めにご相談ください。
股関節の痛みの原因となる生活習慣や外傷、障害など
股関節は深い位置にあるため、痛みの場所が分かりにくく、「太ももが痛い」「膝が痛い」といった症状が股関節からきていることも珍しくありません。
原因としては、加齢や日常の姿勢の乱れや歩き方のクセ、長時間の立位・座位、加齢による関節のすり減りが挙げられます。また、スポーツや転倒による外傷、骨折後の後遺症、若い頃のけがが時間を経て症状として現れることもあります。さらに、女性に多い「臼蓋形成不全(きゅうがいけいせいふぜん)」のように、股関節の骨の形に先天的な異常がある場合は、年齢とともに変形性股関節症へ進行するリスクが高くなります。
股関節の痛みを引き起こす代表的な疾患
変形性股関節症
日本では女性に多い疾患で、股関節の軟骨が徐々にすり減り、関節が変形して痛みが生じる病気です。主な原因としては、先天性股関節脱臼や臼蓋形成不全が背景にあることが多く、40代以降で症状が現れはじめます。歩き始めや立ち上がり時の痛みから始まり、進行すると常に痛みを感じることや、関節の動きが制限されて靴下を履くのも困難になることがあります。
詳しくはこちら大腿骨頭壊死症
股関節の骨(大腿骨頭)に血液が届かなくなることで、骨が壊死し、痛みや機能障害が生じる病気です。原因はよくわかっていませんが、ステロイドの長期使用や大量飲酒がリスク因子とされ、男性では40代、女性では60代に多くみられます。初期は自覚症状が少ないものの、進行すると骨が潰れて激しい痛みを伴います。特発性大腿骨頭壊死症は指定難病となっています。
鼠径部痛症候群(グロインペイン症候群)
サッカー選手などに多く見られる疾患で、股関節の前方(鼠径部)に痛みが生じる状態です。過度な負荷や繰り返しの運動によって筋肉・腱・靱帯に炎症が起こり、走る・蹴るなどの動作時に強い痛みが出ます。早期のリハビリテーションと運動制限が重要です。
股関節の痛みに伴ってみられやすい症状
股関節の痛みは単独で現れることもありますが、以下のような症状がみられることもあります。
- 太ももや膝の痛み(関連痛)
- 足を動かしたときの引っかかり感や可動域の制限
- 立ち上がり・しゃがみ動作時の不安定感
- 歩行時に左右差が出る
- 靴下やズボンの着脱が困難になる
- 長時間歩けない、疲れやすい など
このような症状がある場合、関節構造の変形や機能低下が進行している可能性があり、放置すると日常生活に大きな支障をきたすおそれがあります。
痛みや変形が強く、日常生活に大きな制限が出ている場合は、人工股関節置換術などの手術治療が必要になることもあります。その際は、連携している高度医療機関と連携を取り、スムーズな紹介を行います。
足の痛み・しびれについて

足の痛みやしびれは、関節や筋肉の障害だけでなく、神経や血流、骨の異常など多くの原因が考えられます。
一時的な症状として軽くみられがちですが、放置してしまうと日常生活に支障をきたすことも少なくありません。当院では、整形外科専門医が原因をしっかりと見極め、正確な診断と症状に合わせた治療で、再発予防や生活の質の改善をサポートいたします。
足の痛み・しびれの原因となる生活習慣や外傷、障害など
足は全身の体重を支える重要な部位であり、歩く・立つ・階段を昇り降りするといった動作のたびに、大きな負荷がかかっています。こうした動作の繰り返しにより、関節や筋肉、靱帯に炎症や損傷が生じることが、痛みやしびれの原因となります。
また、長時間の立ち仕事や運動、歩行量の多い生活習慣も、足に負担をかける要因となります。足に合わない靴や硬い路面でのランニングも、足裏・かかと・ふくらはぎなどに慢性的な障害を起こすことがあります。さらに、腰椎由来の神経の圧迫(坐骨神経痛 など)や血流障害、糖尿病性神経障害といった全身性疾患が、足のしびれや痛みの原因になることもあるため、症状のある方はお早めにご受診ください。
足の痛み・しびれを引き起こす代表的な疾患
足底腱膜炎
かかとの骨から足指にかけて張っている腱膜に炎症が生じ、とくに朝の一歩目にかかとや足裏が強く痛むのが特徴です。長時間の立ち仕事や歩行、スポーツ、加齢による足底のアーチ構造の低下が原因となります。放置すると慢性化しやすいため、早期の対処が重要です。
坐骨神経痛
腰から足先に伸びる坐骨神経が圧迫または刺激されることで、お尻から太もも、ふくらはぎ、足先にかけて鋭い痛みやしびれが走る症状です。原因の多くは、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症です。歩くとしびれが強くなる、長く立っていられないといった症状を伴う場合は、腰の精査が必要です。
モートン病
足の指の付け根にある神経が圧迫されることで、中指と薬指の間に焼けるようなしびれや痛みが出る疾患です。ヒールの高い靴やつま先の狭い靴を履く習慣のある女性に多くみられます。歩行中にしびれが強くなることが特徴で、足底パッドや靴の調整で症状が改善することもあります。
末梢神経障害・糖尿病性ニューロパチー
糖尿病などの代謝性疾患により、末梢神経が徐々に障害を受けることで足先にしびれや感覚の鈍さ、痛みが出る病気です。左右対称にしびれる、靴下をはいているような感覚になるなどが特徴で、進行すると感覚が鈍くなり、傷や火傷に気づきにくくなることがあります。
足の痛み・しびれに伴ってみられやすい症状
足の症状に加えて、以下のような症状がみられる場合には、疾患が進行している可能性があります。
- 足首や膝までの放散痛
- 長く歩くと痛みが強くなり、休むと軽快する(間欠性跛行)
- 足の力が入りにくい、足がもつれる
- 足先の感覚が鈍くなる、冷たく感じる
- 皮膚が乾燥し、傷が治りにくくなる(血流障害) など
これらの症状がある場合は、神経や血管が深く関与している可能性があるため、早めの精密検査と整形外科での診断が推奨されます。糖尿病など血流や代謝が関係している場合には、内科的疾患との連携を行いながら、全身の健康状態を見据えた治療が重要となります。
足の痛みやしびれは、「疲れ」や「年のせい」と思われがちですが、その背後に治療が必要な疾患が隠れていることも少なくありません。一人で悩まず、少しでも違和感を覚えたら、早めにご相談ください。