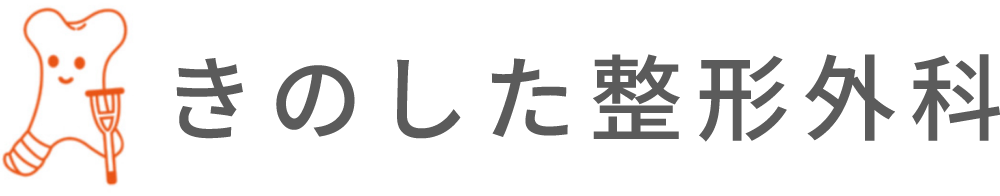骨粗鬆症とは

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)とは、骨の強さが低下し、もろく折れやすくなる病気です。年齢を重ねるとともに、骨の密度や質は自然と低下していきますが、骨粗鬆症になるとその進行が早まり、ちょっとした転倒や衝撃で骨折を引き起こしやすくなります。この病気はとくに女性に多く見られ、なかでも閉経後の女性では、女性ホルモンの減少によって骨の吸収が進み、骨量が急激に減ってしまいます。
日本では高齢化の影響もあり、現在、骨粗鬆症の推計患者数(40歳以上)は1,590万人(女性1,180万人、男性410万人)とされています。女性のリスクは男性の約3倍ですが、男性のリスクも高まりつつあり、骨粗鬆症による骨折がきっかけで寝たきりになるケースも少なくありません。骨粗鬆症は、骨折だけでなく、その後の生活の質や介護の必要性にまで大きく関わってくる疾患であるため、注意が必要です。
骨粗鬆症の原因
骨粗鬆症の主な原因としては、加齢やホルモンの変化が挙げられます。人の骨は、常に古い骨が壊され、新しい骨が作られるというサイクルで保たれていますが、年齢を重ねると骨を作る力が弱くなり、骨を壊す力の方が強くなっていきます。とくに女性は閉経によりエストロゲンという骨を守るホルモンの分泌が減るため、骨量の減少が加速します。また男性もテストステロン(男性ホルモン)の減少が骨量低下につながります。
一方で、運動不足やカルシウム・ビタミンDなどの栄養不足といった生活習慣も、骨の質を低下させる原因となります。20歳以上の女性では、カルシウムの一日の摂取量が推奨される量よりも少ないという統計結果が出ており、これが将来の骨粗鬆症の発症にもつながってしまいます。
また過度な飲酒や喫煙といった生活習慣、さらに糖尿病や関節リウマチ、腎疾患、甲状腺機能亢進症などの慢性疾患も骨粗鬆症の要因になるとされており、ステロイド薬など一部の薬剤の影響でも骨密度が低下することが知られています。
このように骨粗鬆症は単に「年を取ったからなる病気」ではなく、生活習慣や体質、病気の影響などが重なり合って発症する病態と言えます。
骨粗鬆症の症状
骨粗鬆症は初期には自覚症状がほとんどなく、気づかないまま進行するのが特徴です。そのため、骨折をきっかけに診断されることも少なくありません。骨粗鬆症を起因とする骨折には、以下のようなものがあります。
圧迫骨折(脊椎圧迫骨折)
背骨の骨が押しつぶされるように潰れてしまう骨折で、尻もちをつくなどの軽い衝撃でも起こることがあります。突然の腰痛、背中の痛み、身長の低下、猫背などが見られます。
大腿骨近位部骨折(股関節の骨折)
転倒などが原因で太ももの付け根部分が折れる骨折で、要介護状態や寝たきりの大きな原因になります。
上腕骨近位端骨折
腕の付け根(肩の近く)に起きる骨折で、転倒時に手をついた際などに起こりやすく、肩の痛みや関節の可動制限を引き起こします。
橈骨遠位端骨折(手首の骨折)
手をついて転んだときに多く見られる骨折で、高齢女性にとくに多いです。こうした骨折をきっかけに要介護状態へと進行することもあり、骨粗鬆症の予防や早期発見は生活の質を守るうえで非常に重要です。
これらの骨折は、日常の中で起こるちょっとした転倒でも生じてしまい、骨折後の回復には長い期間を要し、とくに高齢者では寝たきりや要介護状態になる大きな原因になります。骨粗鬆症は放っておくと、生活の質を一気に落としてしまうリスクがあるため、症状がなくても定期的なチェックや早期の対応が重要です。
骨粗鬆症の検査と診断
骨粗鬆症かどうかを診断するためには、以下のような検査を行います。
骨密度検査

最も基本的な検査で、骨の強さ(密度)を数値化して評価します。当院では「DXA(デキサ)法」という、より正確に骨密度を測定できる機器を使用しています。主に腰椎と大腿骨で測定を行います。
X線(レントゲン)検査

圧迫骨折などの有無や骨の形状を確認するために行います。すでに骨折が進行している場合、背骨の変形などが見られます。
血液検査・尿検査
骨の代謝(骨吸収・骨形成)の状態を確認するため、骨代謝マーカーを測定します。二次性骨粗鬆症の原因となる疾患のスクリーニングにも役立ちます。
骨密度は年齢や性別によって基準が異なるため、測定結果をもとに総合的に診断します。検査は比較的簡単で痛みも少なく、短時間で終わるものですので、気になる方は早めに受けておくことをおすすめします。
骨粗鬆症の治療
骨粗鬆症の治療は、骨折のリスクをできるだけ下げることを目的として行われます。治療にはいくつかの方法がありますが、薬物療法・栄養療法・運動療法をバランスよく行っていきます。
薬物療法
骨の代謝バランスを整えるさまざまな薬剤があります。患者様の年齢、骨折リスク、他の疾患や服薬状況を踏まえ、一人ひとりに合った薬剤を選択します。代表的なものは以下の通りです。
ビタミンD製剤
カルシウムの吸収を助け、骨の形成を支えます。
ビスホスホネート製剤
骨吸収を抑え、骨密度を改善します。週1回・月1回などの服用や注射があります。
選択的エストロゲン受容体修飾薬(SERM)
骨を壊す働きを抑えて骨量の低下を防ぎます。
アバロパラチド
骨芽細胞を活性化させて骨の形成を促進する薬剤です。1日1回自己注射する製剤です。
デノスマブ
6ヶ月ごとの皮下注射で骨吸収を抑制します。骨折予防効果も高く、使用頻度が少ないのが特長です。
ロモソズマブ
骨の形成を促進する作用と、骨吸収を抑制する作用があります。
副甲状腺ホルモン製剤(PTH製剤)
骨を作る力を促進する注射薬で、重度の骨粗鬆症に用いられます。
運動療法
骨に適度な負荷をかけることで骨の新陳代謝を促します。ウォーキングや軽い筋トレなどの継続的な運動習慣が予防・治療の両面で効果的です。また、転倒予防のためのバランス訓練も重要です。日光を浴びることで体内のビタミンDが活性化されるため、屋外での軽い運動も推奨されます。
骨粗鬆症は放置すれば将来的に骨折を招き、生活の自由や自立性を失うリスクを高める疾患です。ですが、早期に発見し、適切に治療することで予防や進行抑制は十分に可能です。
「最近、背中が丸くなった気がする」「親が骨粗鬆症だったので心配」「転倒が増えてきた」といった気になることがあれば、お気軽に当院にご相談ください。骨の健康を守ることは、これからの人生を自分らしく過ごすための大切な一歩です。