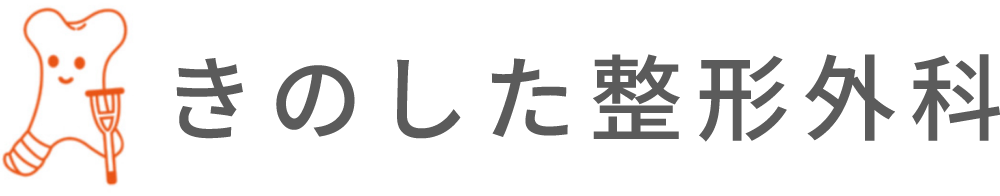関節リウマチ

リウマチという言葉は、さまざまな関節の痛みを生じる疾患に対して使われることがありますが、整形外科でリウマチと言えば、正式には全身性の自己免疫疾患である「関節リウマチ」というものです。
これは主に関節の内側にある滑膜という組織が、自己免疫の異常によって慢性的な炎症を起こし、放置すると関節の破壊や変形を引き起こす疾患です。患者様の約8割が女性で、男性よりも女性の方が約4倍発症しやすいとされています。30~50代で発症することが多く、とくに働き盛りである40代での発症が多くみられます。
関節リウマチは、早期に発見し、適切な治療を行えば、症状の進行を抑え、日常生活に大きな支障をきたさずに過ごすことも可能になってきています。当院では関節の状態を丁寧に評価し、薬物治療やリハビリテーションなどを行っていきます。一度破壊された軟骨・骨・関節は元に戻らないため、早期診断・早期治療が非常に重要になりますので、気になる症状がありましたら、お早めにご相談ください。
こんな症状がある場合、関節リウマチが疑われます
- 朝、起きた時に手足などの関節がこわばって、10分~1時間以上続く
- 手の指や手首、膝、足首などの関節が腫れて痛む
- 関節の腫れが数週間以上続いている
- 左右対称に関節が痛む
- 瓶のふたが開けられない、開けるときに関節が痛い
- 重いものを持つと手首が痛い、ドアノブが回しにくい
- 歯ブラシが持ちづらく、うまく歯が磨けない
- 上手くボタンがはめられない、靴紐が結べない
- 上手く箸やハサミなどの道具が使えない
- 階段を上り下りすると膝関節が痛い
- 入浴すると体中が痛むことがある
- 全身がだるく、熱っぽさも感じるときがある など
関節リウマチの症状の特徴
関節リウマチの初期症状では、手指の第2関節や手首、足の指など、小さな関節に炎症が起こることが多く、両手両足の同じ場所に痛みや腫れが見られることが特徴です。炎症が続くと、関節の軟骨や骨が破壊され、関節が変形し、動かしにくくなっていきます。進行すると、関節の動きが制限されるだけでなく、日常生活の基本的な動作(箸を持つ、服を着る、階段を上るなど)が困難になってしまうこともあります。
また、関節だけでなく、肺、心臓、皮膚、眼など全身に炎症が及ぶ「関節外症状」が現れることもあり、微熱、疲労感、食欲低下などの全身倦怠感がみられることもあります。そのため、関節リウマチは「関節の病気」としてだけではなく、「全身の炎症性疾患」として対応していくことが必要となります。
関節リウマチの原因と発症のしくみ
関節リウマチは、「自己免疫疾患」と呼ばれる病気の一つです。免疫とは、本来ウイルスや細菌などの外敵を攻撃する身体の防御システムですが、関節リウマチではこの免疫が自分自身の正常な関節の組織(とくに滑膜)を「異物」と誤認して攻撃してしまいます。その結果、関節内に慢性的な炎症が起き、時間の経過とともに関節構造が破壊されていきます。
原因はまだ完全には解明されていませんが、遺伝的な体質に加え、感染症、喫煙、歯周病、ストレス、腸内細菌の乱れなどが発症に関与していると考えられています。女性に多くみられることや、妊娠・出産を機に症状が変化することなどから、女性ホルモンが関係している可能性も指摘されています。
関節リウマチの検査と診断
関節リウマチの診断には、医師による問診と診察に加えて、血液検査や画像検査を組み合わせて行います。血液検査では、炎症の程度を示すCRPや赤血球沈降速度(ESR)、リウマトイド因子(RF)や抗CCP抗体など、リウマチ特有の項目を確認します。これらの数値が陽性でもすぐに診断がつくわけではなく、ほかの疾患との鑑別が必要になることもあります。
画像検査としては、レントゲンで関節の変形や骨のびらんを確認するほか、超音波検査やMRIを用いて、より詳細に滑膜の炎症や骨の状態を評価します。初期の関節リウマチは見た目の腫れや痛みだけでは判断が難しいこともあるため、さまざまな角度からみていくことが診断には重要になります。
関節リウマチの治療
関節リウマチの治療は、「痛みを抑える」ことにとどまらず、「関節を守り、できるだけ長く自立した生活を続ける」ことを目標に行われます。現在では治療の選択肢が広がり、薬物療法に加え、リハビリテーションや手術療法を組み合わせることで、日常生活の質(QOL)を保ちながら進行を防ぐことが可能となっています。
薬物療法
関節リウマチの基本的な治療は、薬によって炎症や免疫異常を抑えることです。第一段階では抗リウマチ薬が使用され、効果が不十分な場合、第二段階として生物学的製剤やJAK阻害薬が追加されます。それでも効果がみられない場合は、生物学的製剤やJAK阻害薬の種類を変えていきます。どの薬も効果が期待できるものですが、副作用もあるため、医師の指示に従って、経過をみながら使用していくことが必要です。
リハビリテーション
関節リウマチでは、関節の動きを維持し、日常生活の自立を支えるリハビリテーションが欠かせません。痛みの程度や関節の状態に応じて、以下のようなリハビリが行われます。
理学療法(PT)
関節の可動域を保ち、筋力や体力の低下を防ぐために、関節可動域訓練(ROM訓練)や筋力強化運動(レジスタンストレーニング)を行います。使用される器具には、セラバンド、エアロバイク(エルゴメーター)、バランスボールなどがあります。痛みがある時期にはホットパックや超音波療法による物理療法も併用されます。
作業療法(OT)
手指や上肢の細かな動作を改善し、日常生活動作(ADL)の支援を行います。使用される器具には、ペグボードや握力ボール、自助具(スプーンの持ち手、ボタンエイド など)があり、箸の使い方や衣服の着脱など実生活に直結した練習が行われます。関節を保護する動作指導も併せて行われます。
装具療法
関節の安定を保ち、痛みを軽減する目的で装具やサポーターを使用します。たとえば、手関節用のスプリント(支持装具)や、指の変形予防用装具、膝や足首の支えとなる短下肢装具などが用いられます。装具は作業療法士と連携し、個々の症状に合わせた調整を行います。
手術
薬物やリハビリで症状が改善しない場合や、関節の破壊が進行して機能障害や強い痛みがある場合には、手術療法が検討されます。手術を行う場合は、連携する専門の医療機関をご紹介します。
滑膜切除術
関節リウマチによる関節滑膜の炎症で生じる痛みや関節可動域の制限に対し行われる手術です。炎症で腫れた滑膜を切除することで、疼痛を取り除きます。軽度から中等度の関節炎・破壊がある関節が対象となります。頸椎を除くほぼ全ての関節で可能で、主に肘、手首、指、足首などで行われます。関節内視鏡を用いる方法や関節を開ける方法があり、骨や軟骨にはほとんど触れません。良好な成績が期待できますが、再発の可能性もあります。
人工関節置換術
関節炎や変形・破壊が進み、痛みや動きの制限で日常生活に大きな支障がある場合に行われます。すり減った関節の骨や軟骨を取り除き、人工の関節に置き換えることで、痛みなく日常生活を送れるようにすることが目的です。以前は主に膝関節と股関節で選択されていましたが、近年は肩、肘、指、手、足、足趾など多くの関節で行われるようになりました。手術により痛みはほとんどなくなりますが、違和感がなくなるまで時間を要する場合があります。また人工関節には寿命があり、部位や患者様の活動度により異なりますが、膝・股関節では約20年とされています。
関節固定術
関節破壊が著しい場合や、人工関節が使えない、または安定性が期待できない場合に行われる手術です。関節を機能しやすい角度で完全に動かなくなるように固定することで、確実な痛みの除去と、ぐらつかない安定性を得ることを目的とします。主に首の骨(頸椎)、手首、足首、指(とくに母指)、足の親指などで行われます。関節が動かなくなるため、日常生活動作に制限が生じるという側面があります。このため、近年では行われる頻度は減少傾向にあります。ただし足首の固定術では、足部の他の関節は動くため、全く動かなくなるわけではありません。
関節形成術
近年の薬物療法の進歩により、自分の関節を可能な限り温存したいというニーズから増加している手術です。関節の構造が比較的残っている初期から中期の病状で行われます。関節の一部を削るなどして形を整え、関節の機能や見た目を改善することを目指します。主に肘、手首、指、足の指などで多く行われており、これらの部位では手術治療の中心となることもあります。この手術は、人工関節のように完全に置き換えるのではなく、自身の関節を活かす点が特徴です。また関節の変形に伴って切れてしまった腱を、移行したり移植したりして付け替える手術が行われることもあります。