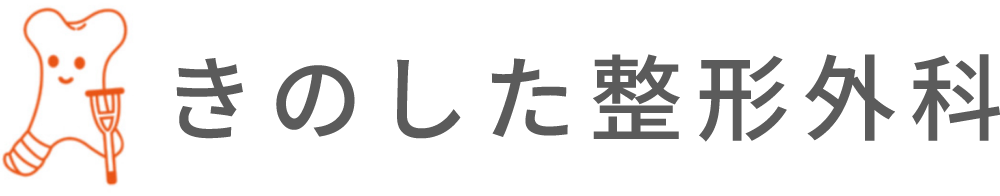外傷とは

外傷とは、日常生活やスポーツ、事故などによって体に生じた急性の損傷やけがの総称です。骨や関節、筋肉、靱帯、皮膚、神経、血管など、体のあらゆる部位に外からの力が加わることで損傷が生じ、痛みや腫れ、変形、出血などの症状が現れます。
軽い打撲やすり傷で済むこともあれば、関節の脱臼や骨折、脊髄の損傷といった深刻な障害に至る場合もあり、その重症度はさまざまです。整形外科では、これらの外傷を専門的に診療し、適切な処置と早期回復を目指す治療を行っています。
主な外傷の種類
外傷には非常に多くの種類がありますが、大きく分けると、皮膚や軟部組織に損傷を及ぼす「切創」や「挫創」などの外表性外傷、骨・関節・靱帯などに影響を及ぼす「骨折」「捻挫」「脱臼」などの運動器外傷、神経に影響を及ぼす「脊髄損傷」などの中枢性外傷に分類されます。
それぞれの外傷は、原因や症状、必要な治療法が異なります。適切な診断と早期の治療が、その後の回復に大きく影響するため、早めの受診が重要です。
外傷の主な原因
外傷は、日常の不注意による転倒や打撲、台所や作業中の切り傷、スポーツ中の衝突や過負荷、交通事故、災害、加齢による身体能力の低下など、さまざまな場面で発生します。
高齢者では骨や関節の脆弱性が原因で、ちょっとした転倒でも骨折や脱臼を引き起こすことがあります。お子様では運動量が多いため、走り回る中での転倒や衝突によるけがが多くなります。スポーツをする方では、繰り返される動作による障害や、高負荷の瞬間的な衝撃による外傷が多く見られます。
以下のような外傷の診療を行っています
切創
切創とは切り傷のことで、刃物や鋭利な物によって皮膚や皮下組織がスパッと切れた状態を指します。料理中の包丁やガラスの破片、金属片などが原因になることが多く、日常生活でも負いやすいけがです。
表皮のみに傷がとどまった場合は、出血しても患部を圧迫することで止血できることがあります。傷が真皮に至ってしまうと白い真皮部分が露出することがあり、さらに下の皮下組織まで損傷が及ぶと皮下脂肪が見え、傷口が大きく開くこともあります。そうした場合、必要に応じて縫合処置を行います。傷が表皮までであっても、細菌感染を防ぐため、しっかりと洗浄することが必要です。場合によっては抗菌薬を使用することもあります。
皮膚の切り傷に加えて神経や血管、腱、筋肉、靱帯などが傷つけられている場合は、早急な専門的処置が必要ですので、すぐに医療機関をご受診ください。
挫創
挫創は挫滅創や打撲創などとも呼ばれるもので、鈍い力が加わった際に皮膚や筋肉がつぶれたり裂けたりする外傷のことです。交通事故や転倒、スポーツ、重い物に挟まれたとき、何かに強く打ちつけたときなどに起こります。切創と違い、出血は少なくても組織の奥深くまで損傷していることがあり、骨折や神経の損傷を伴うこともあるなど高度な外傷になることがみられます。
感染や壊死のリスクが高まる場合もあり、傷の処置には洗浄やデブリードマン(壊死組織の除去)が必要で、場合によっては入院管理や再建手術が必要になることもあります。見た目以上に重症化しやすい外傷ですので、早めの医療期間の受診が推奨されます。
打撲
打撲は、転倒やぶつけるなど、外からの強い力によって、皮膚の表面に傷はないものの、その下の皮下組織や筋肉、血管が損傷を受ける外傷です。一般的に「青アザ(内出血)」や「たんこぶ(皮下血種)」といった症状が現れます。これらは血管が切れることによって引き起こされます。また筋繊維が損傷すると、痛みや腫れが現れます。転倒や交通事故、サッカーやラグビーなどのスポーツ等においてよくみられ、とくに体のバランス感覚が未熟なお子様では、転倒による打撲が多くなっています。
打撲の症状は多くの場合、時間の経過とともに改善しますが(数日程度)、内出血が広がると強い腫れや痛みが続くことがあります。打撲部位が関節周囲に及ぶと、関節内血腫や靱帯損傷を合併していることもあります。痛みで動かさないでいると可動域が狭くなったり、筋力が低下して回復が遅くなったりしてしまいます。アイシングや安静が初期治療になりますが、痛みがなくなったら、早期から可動域を広げるリハビリや、装具(サポーター など)の使用が重要です。
痛みが強い、腫れが引かない場合は、骨折や深部損傷を見逃さないよう整形外科での診察をおすすめします。
捻挫
捻挫とは、関節に無理な力が加わり、関節を支える軟部組織(靱帯や腱)、軟骨(関節軟骨や半月板、関節唇)といった周囲の組織が傷ついた状態で、骨折や脱臼を除いたものです。レントゲン(X線)で写らないものが捻挫とされ、足首のひねりや転倒、スポーツ中の接触などでよく見られます。
軽度の捻挫では腫れや痛みが主な症状となりますが、損傷した部位によっては、あまり痛みを感じないこともあるため、痛みがないからと放置してしまわないようにしましょう。関節内の傷は積み重なると変形性関節症のような状態になることがあるため、注意が必要です。
治療では、冷却や圧迫、安静を行い、必要に応じてサポーターや装具を使用します。靱帯が部分的に切れていたり、関節内に出血していたりする中等度以上の捻挫では、固定するなどの治療が必要です。放置すると靱帯が緩んで関節がぐらぐらするなど不安定になり、再発を繰り返すこともあります。場合によっては手術が必要なこともあります。いずれにしても、リハビリを行うことが大切です。
脱臼
脱臼は、関節の骨が本来の位置から完全にずれてしまう状態で、肩、肘、指、股関節などでよく発生します。また顎の関節でも起こることがあります。ちなみに少し外れた状態は「亜脱臼」と呼ばれます。転倒や衝突、強い力で関節がねじられたときに起こり、脱臼部位では強い痛みや変形、動かせないといった症状が現れます。
主にラグビーや柔道などのコンタクトスポーツでよくみられ、転倒や交通事故などの日常においても脱臼が起こることもあります。
治療では、まず速やかに関節を元の位置に戻す整復を行い、その後は関節を安定させるための固定が必要です。整復時には局所麻酔や全身麻酔が必要になることもあります。無理に自分で戻そうとすると神経や血管を傷つける恐れがあるため、必ず医療機関で処置を受けてください。整復後には装具などで関節が動かないように固定します。再発しやすい場合は手術が検討されます。
骨折
詳しくはこちら関節損傷
関節損傷とは、捻挫や脱臼などに伴って、関節内の軟骨、靱帯、半月板、関節唇などが外傷によって損傷した状態で、膝や肩、足首などの大きな関節で多く見られます。スポーツ中のねじれ動作やジャンプの着地、転倒などで生じます。また加齢に伴う変形性関節症でも関節損傷が引き起こされる場合があり、リウマチ性疾患や炎症性疾患でも発症することがあります。
症状としては、痛みや腫れ、引っかかり感、不安定感などがみられます。症状が一時的に軽快しても、病態によっては損傷が進行していることもあるため、MRIなどの画像検査が重要です。放置してしまうと、慢性的な痛みに悩まされたり、機能が低下したり、股関節などの場合は寝たきりになって要介護となるなど、大きく生活の質を落としてしまう場合があります。
治療は損傷の程度に応じて保存療法(リハビリ、装具)または手術療法(関節鏡手術 など)が行われます。早期に適切な治療を行うことで、関節機能の回復と再発予防が期待できます。
脊髄損傷
脊髄損傷は、事故や転落などによる強い衝撃によって、脊椎が骨折や脱臼をするなどし、脊椎の中を通る神経(脊髄)が損傷されるという重篤な外傷です。日本では、年間で約5000人の脊髄損傷の患者様が発生しています。原因は、交通事故、転落、転倒などが主なもので、高齢化が進む日本では高齢者の転倒による受傷が増加傾向にあります。
脊髄損傷の程度には、損傷された脊髄の遠位の運動、感覚機能が完全に消失している状態の「完全麻痺」と、脊髄の一部が損傷し、脊髄損傷部位の遠位のなんらかの運動もしくは感覚機能が残存している状態の「不全麻痺」があります。損傷の部位や程度によって、四肢の麻痺、しびれ、感覚障害、排尿・排便障害などの症状が現れます。頸椎や胸椎、腰椎の骨折を伴うことも多く、救急対応が求められます。
治療は、初期には安静や固定によって損傷の広がりを予防します。残念ながら、脊髄損傷を完治させる方法ありません。不全麻痺では外科的な減圧手術が行われる場合があり、急性期を過ぎましたらリハビリによる機能回復が中心となります。残った機能を最大限に生かすためにもリハビリテーションに取り組んでいくことが重要になります。